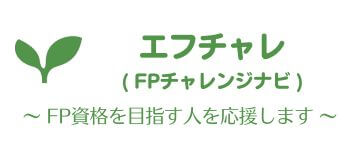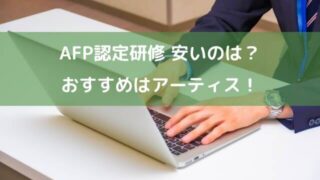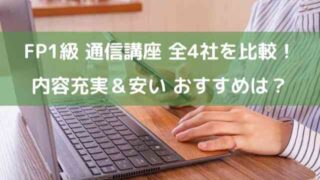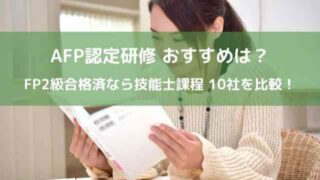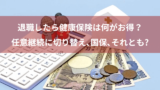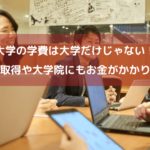奥さんや旦那さんがパートで働く際の「年収の壁」って知ってますか?
- 103万とか150万とか聞くけど収入にどう影響するの?
- 取りあえず130万は超えないように言われたけど、あとはよく分からない
- 今年から控除の制度が変わったらしいけど、、、
なんとなくパート仲間など人づてで金額は聞いてても金額の理由がよく分からなかったり、それ以外の年収の壁については知らない人が多いようです。
この記事では税金と社会保険に存在する合わせて5つの年収の壁について詳しく説明しますので、これを読めば、
- 5つの年収の壁の金額が分かる
- 各々の壁を超えることによる収入(手取り)への影響が分かる
- 各々の壁への対処が分かる
よって、パートの契約にあたって自分の希望する収入や働き方に合った就業時間や期間を決められるようになります。
税金と社会保険に存在する「年収の壁」を説明しますので、ぜひ働く際の参考にしてください。
なおこの記事では便宜上、配偶者のうち納税者を「夫」と記載し、その扶養に入ってパートで働く配偶者を「妻」と記載して説明しています。
分かりやすさのためですのでご了解ください。
年収の壁:税金は98万円、103万円、150万円

パート収入が増えると所得税、住民税に影響してきます。
年収の壁1:98万円を超えると住民税の所得割
住民税の所得割は収入から控除額を差し引いた後の所得に対してかかります。
控除は基礎控除と給与所得控除です。
1つ目の基礎控除はパート勤務に限らず自営業も含めて誰でも控除されるもので、基礎控除の額は43万円です。(所得が2,400万円以下の場合)
2つ目の給与所得控除はパート、バイト、正社員などの給与所得に対して定められている控除です。
給与所得控除は収入額によって控除額の算出式が変わりますが、給与収入1,625,000円以下の場合は給与所得控除の額は55万円で定額です。
まとめると、基礎控除が43万円、給与所得控除が55万円で合計98万円が控除額です。
つまり年収が98万円を超えると超えた分に対して住民税の所得割が発生しますので、これが1つ目の年収の壁です
年収の壁2:103万円を超えると所得税
所得税も収入から控除の額を差し引いた所得に対してかかります。
所得税の控除も基礎控除と給与所得控除の2つです。
基礎控除は住民税の場合よりも5万円多くて48万円、給与所得控除は住民税の場合と同様に55万円で、合計すると控除額は103万円になります。
つまり年収が103万円を超えると超えた分に対して所得税が発生しますので、これが2つ目の年収の壁です。
年収の壁3:150万円を超えると配偶者特別控除が減少
パート収入が増えると本人だけでなく配偶者の所得税にも影響してきます。
夫の扶養に入っている妻がパートで働く場合には、夫の配偶者控除、配偶者特別控除に影響する可能性があります。
配偶者控除の壁は無い
配偶者控除の条件は夫と妻の双方にあります。
夫の条件は所得が1,000万円以下であることです。
夫の所得金額に応じて配偶者控除の控除額が変わります。
| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
妻の条件は所得が48万円以下であること、つまり給与所得控除を足して年収が103万円以下であれば配偶者控除を受けられます。
ただしこれを超えても配偶者特別控除になるだけですので、実質的には配偶者控除としての壁はありません。
配偶者特別控除の壁は150万円
配偶者特別控除の条件も夫と妻の双方にあります。
夫の条件は配偶者控除と同様、所得が1,000万円以下であることです。
夫の所得金額が900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1000万円以下の3段階で配偶者控除の額が変わります。
妻の条件は所得金額ですが、所得金額に応じて控除額が段階的に変わります。

(出典: 国税庁 配偶者特別控除)
上の表で配偶者の合計所得金額は今回は妻のパート給与所得ですが、分かりにくいのでポイントとなる金額を給与所得控除前の年収に換算しておきます。
- 所得:48万円 ⇒ 年収:103万円
- 所得:95万円 ⇒ 年収:150万円
- 所得:133万円 ⇒ 年収:201万円
つまり年収103万円を超えても150万円までは配偶者控除と同額の控除を受けられることが分かります。
しかし150万円を超えると段階的に控除額が減っていき201万円を超えると配偶者特別控除が無くなることが分かります。
年収が150万円を超えると配偶者特別控除が減り始めますので、これが3つ目の年収の壁です。
税金ではないけど扶養手当に注意
夫の会社から妻の扶養手当が支給されている場合は注意が必要です。
一般に妻の所得が48万円(年収で103万円)を超えると扶養手当が支給されなくなります。
仮に扶養手当が月に15,000円とすれば年間で18万円が支給されています。
年収103万円を僅かに超えただけで扶養手当の18万円が無くなってしまうので、夫婦としては手取り収入が減ってしまうこともあります。
年収の壁:社会保険は106万円か130万円 または勤務日数・時間
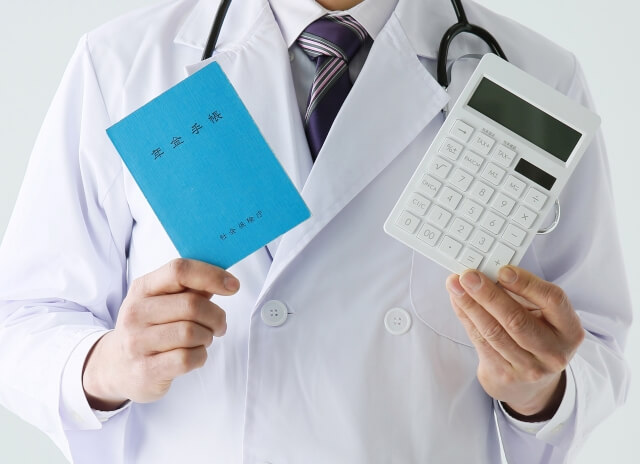
現行の社会保険制度では妻のパート収入が少ない間、具体的には年収で130万円未満なら、社会保険は夫の扶養に入るため自分で社会保険料を支払う必要はありません。
(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある場合は180万円未満)
しかしパート収入が増えてくると自分で社会保険料を負担しなければならなくなります。
働く条件によって「106万円の壁」か「130万円の壁」のどちらかに当たります。
年収の壁4:106万円を超えると社会保険料の負担も
次の条件にすべて当てはまるようなパート勤めをすると社会保険に加入する(=給料の中から社会保険料を負担する)ことが義務付けられています。
- 従業員(厚生年金の被保険者数)が101人以上(2024年10月からは51人以上)の企業に勤務している
- 収入が月88,000円以上
- 勤務期間が2ヶ月以上またはその見込みがある
- 所定労働時間が週20時間以上
- 学生ではない
月88,000円の収入は年収で約106万円です。(8.8万円×12ヶ月=105.6万円)
上の条件に当てはまる人が年収106万円を超えると社会保険料の負担が発生しますので、これが4つ目の年収の壁です。
なおこれで厚生年金保険料、健康保険料を負担することになったら、その後収入が増えても保険料が増えていくだけなので、このあとは社会保険の壁はありません。
一般社員の3/4以上働いても社会保険料の負担が発生
1ヶ月の所定労働日数と1週間の所定労働時間が、同じ事業所で同様の業務を行っている一般社員(常時雇用者)の3/4以上になると厚生年金保険料、健康保険料を負担することになります。
これは年収や会社の規模などに関係なく発生する義務ですから注意が必要です。
年収の壁5:130万円を超えると全員が社会保険料を負担
勤める会社の規模が小さいなど、上の106万円の壁に当てはまらない人も、年収が130万円を超えると社会保険料の負担が発生します。
夫の社会保険の扶養に入っていられるのは年収130万円までですから、それを超えると扶養から出されてしまいます。
勤め先の厚生年金、健康保険に加入できない場合は、自分で国民年金、国民健康保険に加入して年間で数十万円の保険料を支払うことになります。
年収130万円を超えると誰でも社会保険料の負担が発生しますので、これが5つ目の年収の壁です。
夫が既に退職している場合は?
ここまでは、夫が現役の会社員で会社の健康保険に加入していて厚生年金の加入者(被保険者)であるケースを前提に記述してきました。
では夫がすでに退職していて会社勤めをしていない場合は「年収の壁」はどうなるのでしょうか。
年金は「年収の壁」は無い
夫は会社勤めをしていないわけですから国民年金の第1号被保険者、あるいは年齢によっては、すでに国民年金の被保険者ですらありません。
よって夫が会社勤めを辞めた時点で、妻は自分の勤め先で厚生年金に加入していない限り、自分で国民年金に加入して保険料を払う必要があります。
その後、パート勤務で収入が増えて勤め先の厚生年金に加入することになっても金額は上下するかもしれませんが引き続き保険料を支払うことになります。
従って年金については、とくに「年収の壁」はありません。
健康保険は夫の状況による
健康保険については夫の状況によって2つのケースがあります。
夫が国民健康保険(国保)に移行しているケース
夫が会社を辞めて健康保険を国民健康保険(国保)に移行しているケースです。
このケースでは、妻は自分の勤め先で健康保険に加入していない限り、自分で国民健康保険に加入して保険料を払う必要があります。
(実際には世帯主が世帯分をまとめて保険料を支払います)
その後、パート勤務で収入が増えて勤め先の健康保険に加入(国保からは脱退)することになっても金額は上下するかもしれませんが引き続き保険料を支払うことになります。
従ってとくに「年収の壁」はありません。
夫が引き続き会社の健康保険に加入しているケース
会社を辞めても2年間は引き続き会社の健康保険に加入できる「任意継続(任継)」という制度があります。
さらに会社によっては、その後も引き続き75歳になるまで加入できる特例退職者医療制度(特例退職被保険者制度)もあります。
夫がこれらに加入している状況で、“妻が被扶養者となる要件”を満たしていれば夫の現役時代と同様に、106万円、130万円が「年収の壁」となります。
ただし“妻が被扶養者となる要件”は気をつける必要があります。
この要件の一つに“被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満(同居の場合)”というのがあります。
要は妻の年収は夫の年収の半分未満でなければいけないということです。
夫が退職後に無職で年金も受給してなければ、この要件を満たせない可能性もあります。
夫の現役時代には気にも留めなかった要件かもしれませんが、退職後は年間収入の確認が必要です。
なお退職後の健康保険については別記事で説明していますので、参考にしてください。
⇒ 退職したら健康保険は何がお得?任意継続に切り替え、国保、それとも?
5つの「年収の壁」と対処

ここまで説明してきた「年収の壁」を一覧にしました。
| パートの年収 | 内 容 |
|---|---|
| 98万円 | 住民税の支払いが発生する |
| 103万円 | 所得税の支払いが発生する |
| 106万円 | 一定の条件の会社で社会保険料の支払いが発生する |
| 130万円 | 上の条件に該当しない会社で社会保険料の支払いが発生する |
| 150万円 | 配偶者(納税者)の配偶者特別控除の控除額が減り始める |
税金の壁(98万円、103万円、150万円)は基本的に気にしなくてよい
年収98万円で支払いが発生する住民税(所得割)、年収103万円で支払いが発生する所得税は、いずれも増えた収入に対して課税されるものです。
年収150万円から始まる配偶者特別控除の減額もパート年収の増加に応じて小刻みに段階的に減額されていきます。
いずれも期待したほど手取り額が増えなくなる年収のラインですが、手取りがマイナスになるわけではないので気にしなくてもよいです。
ただし注意が必要なのは所得税の支払いが発生する年収103万です。
夫の会社から妻の扶養手当が支給されている場合、一般に妻の所得が48万円(年収で103万円)を超えると扶養手当が支給されなくなります。
仮に扶養手当が月に15,000円とすれば年間で18万円の扶養手当を、年収103万円を僅かに超えるだけで失うことになります。
夫婦としての手取りを減らさないためには、扶養手当が減る以上にパート年収をアップしなくてはいけません。
社会保険の壁(106万円、130万円)は要注意
どちらの壁も、それ以前は夫の扶養範囲内のために自分では支払う必要がなかった社会保険料を、いきなり自分で支払うことになる年収ラインです。
社会保険料は年金と健康保険を合わせれば年間で10万円から数十万円かかります。
パートの年収が壁を少し超えただけの金額であれば、それ以前に比べて手取りは明らかにマイナスになります。
とくに年収130万円ぐらいになれば、所得税、住民税もそれなりの金額になってきますので負担感も増します。
社会保険の壁を超える際には、“いくら以上の年収になれば手取りがプラスになるか”よく検討する必要があります。
年収の壁:まとめ

5つの年収の壁のうち税金の3つ(98万円、103万円、150万円)は配偶者の会社で扶養手当が支給されている場合を除いて基本的に気にしなくてよいです。
社会保険の2つの壁(106万円、130万円)は壁を超えた直後は明らかに手取りがマイナスになるので超えるなら大きく超える必要があります。
配偶者の収入は家族のライフプランにも関わってくるので、壁を意識するような年収に近づいてきた段階で慎重に検討するようにしてください。
お金の基礎知識は誰にでも必要です
今回の記事で取り上げたテーマのほかにも、人生で「お金」に関わるシーンはたくさんあります。
その際に基本的な知識が有るか無いかで、結果が大きく違ってきてしまうことがあります。
幅広いお金の基礎知識を学ぶにはFP(ファイナンシャルプランナー)の資格を目指すのが効率的です。
下の記事では、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格が自分のためにも役立つ代表的なシーンを9つ紹介しています。
さらっと読める記事ですので、ぜひチェックしてみてください。
⇒ ファイナンシャルプランナー資格が自分のためにも役立つ9つのシーン!何級まで取ればいい?